●小説家になるには不向きな職業
小説という物は書こうと思えば誰でも書ける。尤もまともな小説を書き上げるためには大量の読書をしていなければならず、読書量の少ない人はどうやったとしてもレベルの高い小説を作り上げることはできない。だからといって読書量が多ければちゃんとした小説が書ける訳でもないのだ。
というのは、文学界には小説家になるには不向きが職業というものが存在するのだ。なぜだかその職業を経験してしまうと、まともな小説を書けなくなってしまうのだ。その職業が持つ何かが小説家に転職することを妨げてしまうのである。
①脚本家
小説家になるには最も不向きな職業の筆頭は「脚本家」である。脚本家は既に仕事で脚本を書いているので、小説も書けると思いきや、小説を書けないのだ。脚本と小説はまるで違う物なのである。脚本家が小説を書いてしまうと、「小説の核」がなく、その小説を使って監督や女優や男優が料理することで初めて成り立つ物を書いてしまうのだ。結局、脚本家は脚本から抜け出せないのである。
②雑誌の編集長
小説家になるには最も不向きな職業の第二は「雑誌の編集長」である。雑誌の編集長は仕事で自分の雑誌に連載小説とか掲載したりするのだが、仕事でそういうことをやっていれば、自分でも小説を書けるのではないかと錯覚してしまう。しかし雑誌の編集は想像以上にエネルギーを奪うものなのであり、そういう人がいざ小説を書いても、小説を書けるだけのエネルギーが残っていないものなのである。
③フリーライター
小説家になるには最も不向きな職業の三番目は「フリーライター」である。フリーライターは仕事で文章を書きまくっているので、確かに文章は書ける。しかもちゃんとした文章を書いて来る。だが、フリーライターの文章は文章がのっぺらぼうなのであり、その文章に個性がないのだ。これは小説家になるには致命的で、小説として形は整っていても、小説として中身のない物を平気で作ってしまうのである。
●小説として核のない小説
今回紹介する本はこの本!
碧野圭著『書店ガール』『書店ガール2』(PHP研究所)
碧野圭はフリーライター上がりである。だから文章はきちんと書けている。表面的には小説としての形を整えている。しかしこの小説は小説の基本が出来ていないし、「小説の核」がないのだ。この作品を文学専門誌の新人賞に出したら、絶対に落とされる。選考委員は「この小説には小説の核がない」とはっきりと言うことだろう。
碧野圭はフリーライターをやっていたから、出版社に伝手があったのであろう。だから新人賞を取らずに作家デビューしたのだが、小説もどきの小説を平気で書いてしまっているのだ。この本自体、最初は新潮社から出版されたが、文庫本はPHP研究所から出版されたことを忘れてはならない。新潮社はこの作品を良しとは判定しなかったということなのである。
この『書店ガール』の主人公は2人で、書店員の27歳の亜紀と、副店長の40歳の理子である。この主人公は作者の人格を分裂させたものであると思われる。読んでみれば解ることだが、この2人は別々の人格ではなく、2人で一つの者なのである。
この2人は仕事で悉く衝突しているのだが、理子が店長になると半年後に書店が閉店されることになる。それを理子と亜紀は協力して危機を脱するのである。この話はそもそもがおかしい。理子は「雇われ店長」なのであって、書店を閉鎖することに関して決定権を持たないのである。
はっきりと言えることは、碧野圭は書店経営をやったことがなく、書店というものを外から見ているということなのである。書店経営が解らないから、とんでもない空想話を作ってしまったということなのである。書店経営で大事なことは経営者なのであって、店長ではないのだ。店長がやる仕事は書店経営の内の一部分だけなのである。
●作者に問題があると、小説にはより悪化した問題となって出て来る
俺がこの小説を読み終わって真っ先に思ったのは、「作者本人がきちんとした恋愛をしたことがない」ということであった。恐らくこの作者は結婚していないだろうし、たとえ結婚していたとしても結婚になっていないのだ。だから店長には彼氏がいないし、書店員も新婚だというのに新婚の感覚がまるでないのだ。
作者が恋愛をしたことがないということは、まともな友情を持ったこともないということである。多分、この小説の二人の主人公は作者の分身なのであり、常に上下関係があるから、対等な立場で友情を育むというのが全くできないのである。
この作者は明らかに他人を見下している。特にお客様のことを思いっきり見下している。少なくともこの作者は書店員の仕事を経験したことがなく、書店員たちを見下せる立場にいる人だということが解る。しかも非常に自己中心的であり、書店業界のことがまるで見えていないのだ。
厄介なのは碧野圭は理屈を捏ねる性格なのに、自分の頭で考えず、常に何かしらの本に頼って生きているということなのである。だから店長が意見を言っても、その意見に説得力がないのだ。本当の職場だったら、そんな意見が絶対に通る訳がないのだ。
この小説は小説の作者に問題があると小説にはより悪化した問題になって出て来る典型例である。この小説自体、書店が抱えていた問題を解決していないのだ。やったことは表面的に問題を取り繕っただけである。作者はフリーライター上がりだから、職場でプロジェクトチームを作って問題を解決していった経験がないのであろう。
●出版不況に於ける書店の変化
現在、日本の出版業界は出版不況なのであるが、これは出版業界自体が引き起こしたのではなく、日本経済がデフレに突入し、それによって起こった現象なのである。だから出版不況を止めることはできないし、出版社が何か悪いことをやっているのでもないのだ。出版社だって出版不況の中で様々な改革を打ち続けているのである。
①総合書店の登場による弱小書店の淘汰
出版不況の中で書店にも変化が起こっている。その最たる物は総合書店の登場と、それによる弱小書店の淘汰である。総合書店に大量の本があるなら、お客様はそちらの方に行くものなのであって、今までのような弱小書店は潰れて行くしかないのである。
②書店のコンビニ化
こういう状況下では弱小書店は「書店のコンビニ化」で生き残るしかない。店内には最大公約数的な物しか置かず、出来る限り店の個性を出さないようにするのだ。こういう書店はチェーン店化が可能であり、全国どこでも安心して買えるからこそ、お客様はやってくるのだ。
③書店の専門化
もう1つの生き残り策が「書店の専門化」である。書店が何かの分野に特化してしまえば、その書店はその分野に興味を持つお客様を惹きつけるのであって、それで商売が成り立つのだ。こういう書店は個人の書店が必要不可欠であって、個人の才覚で仕事を進めて行くしかないのだ。
④インターネットの販売はそんなに増えるものではない
現在、インターネットで本を買うことができるようになっているのだが、インターネットの販売はそんなに増えるものではないのだ。本は自分が実際にその本を手に取って見てみないと、この本が本当に必要なのか解らないものなのである。インターネットでの本の購入は仕事の忙しい人が使うものなのであって、その売り上げのパーセンテージは業界で言われているほど多くはないのだ。
日本の書店は書籍も雑誌も「委託制」になっているのだが、この出版不況では必ずそれを変えていかなければならない。雑誌は委託制でもいいが、「書籍の買取化」を断行しないと、書店はいつまで経ってもまともなビジネスをできないのである。書籍が委託制になっているからこそ、売れない本が書店に投入され続けるのである。
書店が書籍の買取化を実施しない限り、書店の店員たちがどんなにサービスを工夫しても、多少の販売額増額に繋がっても、抜本的な改革にはならない。『書店ガール』はこの肝腎なことに全く触れていないのである。構造が変化している時に、個人の努力を無闇に称賛してはならない。成果のない努力を強いられれば、書店員たちが燃え尽きてしまい、仕事を辞める羽目になってしまうからだ。
●素人同然の書店員たち
日本の書店はデフレ不況に突入する前から、書店に関して「或る重大な問題」を抱えていた。その重大な問題を解決することなくデフレ不況が到来してしまったために、余計に書店はその重大な問題を深刻化させてしまったのである。
その重大な問題とは、
「書店員たちは書店員として専門教育を受けていない」
ということなのである。
日本の書店の書店員たちは素人同然の人たちでなんの教育も受けずに、書店に就職したからということで書店員をやっているのである。これでは書店員として基本ができていないし、質の高いサービスを提供することすら不可能になってしまうのだ。
ドイツでは書店員に対して「マイスター制度」が確立されており、そのために書店員としてしっかりと教育を受けた書店員が書店で働いているのである。彼等は書店員として充分な能力を持っているから、好況不況に関係なく、質の高いサービスをお客様に施すことができるのである。
日本はこの書店員に対するマイスター制度を導入しなければならないのだ。導入しない限り抜本的な解決策にならないのだ。書店員になりたいのなら、大学卒業後に「書店員養成学校」に入学し、そこで二年間、書店員としてみっちり教育を受け、その書店員養成学校を卒業してから書店員として就職すべきなのである。
「書店員マイスター」を持つということは、事実上「修士号」の取得と同じことなのである。大学進学率が50%を超えている以上、学士号ではなんの価値もないのであって、それ以上の何かを持たねばならないのだ。書店員マイスターがあればこそ、書店員として優秀な働きができるのである。
●「80対20の法則」を使えば簡単!
現在、日本は出版不況に喘いでいるのだが、日本全国の書店が書籍や雑誌の売り方を全く変えていないからこそ、書店の収支は悪化していくのである。書籍や雑誌が売れないのなら、なんで売れるように工夫しないのか? 書店の経営が赤字になれば、如何なる書店でも倒産する羽目になるのだ。
書店を改革していくためには「80対20の法則」を使って行くことだ。売れる本は常に上位20%であり、そこを重視していくのだ。逆に下位20%はどうやっても売れないのだから、勇気を出して切り捨てるべきなのである。そうやって店の商品を分別していくと、お客様たちが書いたくなるような商品が揃うことになるのだ。
またお客様に対しても全て平等にサービスを実施するのではなく、大量に買うお客様に対してサービスを充実させるべきなのである。その大口のお客様たちこそがその書店での売り上げの80%を占めることになるのだ。この大口のお客様すら把握していないのが書店の現状なのである。
経営が悪化している書店をどうにかしたいと思うのなら、日本各地の書店を見て回るべきだし、世界各国の書店を見て回って欲しい。普通の経営をやっていては、いずれ経営が行き詰まるのは当たり前のことなのである。観光旅行などしないで、そういう研修旅行をして欲しい。
日本が参考にできるのは、人口や国土や経済規模から言って、西ヨーロッパ諸国なのだ。絶対にアメリカ合衆国ではないのだ。そこを無視して、アメリカ式のやり方を導入するからこそ、最終的には破綻してしまうのである。国際競争力を持つためには、「独自のスタンス」というものをしっかりと持っておくべきなのである。
●この本を書店員たちが喜んで読んでいるようでは、日本の書店は全滅も有り得る
現在、日本はデフレ不況の真っ只中にある。このデフレ不況は日本経済がどうのこうのではなく、冷戦が終結し、大きな戦争の危機がなくなったからこそデフレになり、そのデフレに伴い不況が発生しているのである。覇権国家のアメリカ合衆国は時折戦争をすることで一時的に経済を刺激することができるが、日本や西ヨーロッパ諸国のようにアメリカ合衆国に押さえられている国々ではそんなことできないから、デフレ不況が深刻化しているのである。
デフレ不況下では「リストラによる質の向上」を図り続けなければならない。数を減少させれば質が向上するのだから、会社は社員を削減して社員の質を上げたり、売れない商品の製造販売を中止して質の高い商品だけを売るようにし、既存の販売ルートに頼るのではなく独自の販売ルートを開拓しなければならないのだ。
出版業界では、作家たちは質の高い作品を作らないと生き残れないし、出版社も粗悪品を廃棄し質の高い出版物だけを出すように試みているし、書店員たちも質の高いサービスをしないと生き残れないのだ。出版不況の中で全ての人たちが徐々に変わって行っているのである。
しかしデフレ時の変化は静かに進むものだから、非常に解りにくい。だから出版業界の変化を正しく見るのではなく、出版社や取次を批判し、書店だけがなんとか努力してどうにかすればいいのではないかと間違った考えを抱いてしまうのだ。
デフレ不況下に於いて間違った考え方を取れば全滅することも有り得るのだ。全国の如何なる書店に於いても、インフレ期に起こったような繁栄が戻って来ることはもう二度とないのである。書店員たちが『書店ガール』を読んで読んで喜んでいるようであるなら、日本の書店は全滅も有り得るのだ。
 | Portrait.Of.Pirates ワンピース STRONG EDITION トニートニー・チョッパーVer.2 販売元:メガハウス |
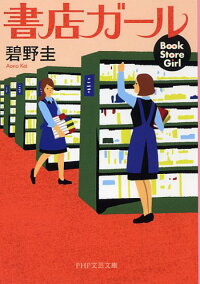
![書店ガール2[碧野圭]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9648/9784569679648.jpg?_ex=200x200&s=2&r=1)